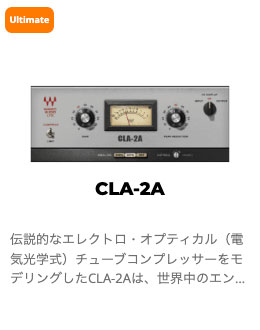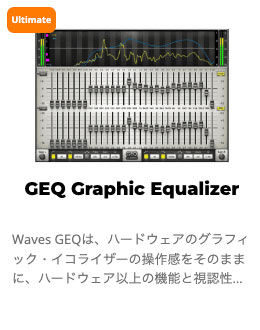My favorite waves 〜Maozon〜
自分にとって初めてのWaves製品はHorizonです。中学生の時に作曲をはじめてもうかれこれ17年ほどになるのですが、当時はMercuryが100万円する時代で “Waves = 初心者には手が出せないプロが使うプラグイン・ブランド” という印象だったので、憧れのWavesを購入できた時はそれはもう...とても嬉しかったですよ。(笑)
普段はクラブサウンドを手がけることが多く、ダブステップやトランスも作っていましたが、最近はドラムンベースを多く制作しているので、そのようなジャンルを制作する上でどのようなWavesプラグインを多用しているのか、僕の使い方も含めてご紹介します。
2025.10.09
My favorite plugins
[Doubler]
おそらくボーカル用途で使用するように作られたであろうプラグインではありますが、僕はベースやウワモノに使うことにハマっています。
これってステレオ・エンハンサーやエキスパンダーだと思っていて、実際にやってることは単純ではあるのですが、パラメータのいじりやすさがすごく気に入っているんですよね。原音を複製してピッチやパンをずらして広がりを出したものを、これ1つでローを削ったりハイを削ったりできるのもいいですね。
[Butch Vig Vocals]
バンドGarbageのドラマーでもあり、The Smashing Pumpkinsの”Gish”やNirvanaの”Never Mind”のプロデュースで知られるButch Vigが監修したボーカル向けチャンネルストリップではあるのですが、自分はこれをドラムバスに使用します。ドラムバスにこのコンプレッサーをかけると、音が太くなるというか存在感がでるというか、とにかくドラムの質感が大きく変わるのでドラム全体の存在感を出す飛び道具です。特に自分のような楽曲ジャンルを作っている人にはおすすめですね。
[CLA−2A]
LA-2Aをモデルにしたプラグインが世の中に無数に存在しているなかで、CLA-2Aはよりアタック感が出て自分好みなんです。正直、実機に触れたことがないので本物らしさという比較はできませんが、とにかくトランジェントが強く出るので、マキシマイザーをかけても物足りない時、前に出したい音にはとにかく何でも使用する感じです。ポップスなどのエンジニアさんからは怒られそうですが、自分は”クリップさせてなんぼ”というスタイルなので、マキシマイザー後のCLA-2Aはオススメです。
ギターにもあえて歪み系エフェクター使うじゃないですか、あのイメージです。
余談ですが自分のミキサーウィンドウは全トラック真っ赤です。(笑)
[GEQ Graphic Equalizer]
最近グラフィック・イコライザーのこの製品をよく使っています。これまでグライコはPAさんが使うものという先入観があり、断然パラメトリック至上主義だったのですが、GEQ Graphic Equalizerは自分がよくイコライジングする500Hzと5KHzというパラメータが存在するので多用しています。何も考えずに任意の帯域を調整できる点がいいですね。頭の中に何キロを下げたいという地図が描けている人には、むしろ分かりやすいかもと思います。
[Renaissance Bass]
定番のR Bassです。気に入っている点は変な持ち上がり方をしない点。フリケンシーの幅が広いのもいいですね。”この音使いたいけどローが足りない”という音ってたくさんあると思うんですけど、そんな時にR Bassを使うと無理なくローを上げてくれるんですよね。EQで同じことをやろうとするとすごく大変ですし、他社でも同じようなプラグインはたくさんあるけれど、R Bassはかかり具合がすごく自然だし埋もれることもないんです。例えば同じキーで鳴らしても、音色によってロー感って様々じゃないですか?自分でもどの帯域を上げていいか迷ってしまう時に、R Bassで持ち上げるとそれだけで解決することも多々ありますね。
[Vocal Rider]
まさに時短ツールですね。指定した音量感でボーカルの音量を一定に保ってくれる便利なツールです。もちろんこれを使用したあとでも突きたい箇所があればオートメーションを書きますが、曲全体でオートメーションを書く必要がないので非常に助かっています。
[H-Delay Hybrid Delay]
主にピンポンの質感が好きで使っています。個人的にはこれに勝るディレイは存在しないと思ってるほどです(笑)。テクスチャーとして楽曲にノイズ感を足したい際に、右下のAnalogというパラメータもいい仕事をしてくれます。サチュレーターを挿す前にこれを使うことで、より自分好みの質感にできるんです。
〜番外編〜
[H-Reverb Hybrid Reverb] ゲート・リバーブ専用機として使っています。
[SSL G-Master Buss Compressor] その名の通りバスコンプとして使っています。
今回は使用頻度の高いWavesプラグインをご紹介しましたが、バージョンアップごとに往年のタイトルのUIが刷新されていたり、L4などの新製品も続々リリースされたりとワクワクさせてくれる大好きなメーカーですので、これを機に再度プラグインを掘ってみようと思いました。みなさんの参考になれば幸いです。
My favorite plugins
プロモーション
人気記事

MIXを始めよう!5つのステップでアプローチ
ミックスと一言で言っても、どこから手をつけたらいいのでしょうか。ローエンド、ボーカル、それともやみくもにフェーダーを触ることでしょうか?ご安心ください。ここでは曲を仕上げるための5つのステップをご紹介

トップエンジニアからの金言。ミキシングのTips
今日は世界一級のエンジニアが送るミキシングのTipsですが、具体的なTips(例えば、EQやコンプをこんな風にセッティングするとか)は1つもありません。しかし、ミックスをするにあたりとても大事なことが数多く含ま

リズム隊のミックスTips! – Vol 4 タム&トップマイク編
ここまでキック、スネア、ハイハットと来ました「リズム隊のミックスTips」。本日はタム編とトップマイク編。いずれもドラム音源にBFD3を使用していますが、他のドラム音源や実際のドラムレコーディングでも参考にな

Waves CA導入事例:ラスベガスの高級ラウンジのサウンドをブラッシュアップ
AVインテグレーション、デザイン、エンジニアリングのリーディングカンパニーとして知られているNational Technology Associates(以下NTA)が米国ネバダ州ラスベガスの新しいダイニング「Todd English's Olives」の

CLA-2A vs. CLA-3A クラシックコンプレッサーの違い
LA-2AとLA-3Aは、最も有名なコンプレッサーと言っても過言ではないでしょう。これまでボーカルやベースなどの楽器に長く愛されてきました。今回は「真空管モデル」と「ソリッドステートモデル」の比較。あなたのトラ

Curves Resolve 2026年1月21日発売!
Wavesから、インテリジェンスなマスキング除去処理を可能にする新製品 Curves Resolve が2026年1月21日(水)に発売されます。
人気製品

Abbey Road Chambers
美しいナチュラルチェンバーリバーブから近年人気が急上昇しているディレイカスケードなど、アビーロードの第二スタジオに設置されたエコーチェンバーの豊かなサウンドは今や伝説となっています。長年に渡って失われ

API 2500
API 2500はAPIパンチ感とAPI独自のトーンを得られる、ダイナミクス・プロセスツールです。デュアルチャンネル・デザインにより、API 2500は1つのコンプレッサー設定で2つの独立したモノ・チャンネルとして動作させる

Bass Rider
Bass Riderは、ベースのトラックにインサートするだけでレベルを自動的に調整する、画期的なプラグインです。人気のプラグインVocal Riderと同じく、使い方もシンプルなBass Riderは、コンプレッサーとは違って、ベ

Bass Fingers
ベースの奏法の中でも最も微細なニュアンスを表現するフィンガーピッキング(指弾き)を再現。リアルなサウンドのベースラインや経験豊富なベースプレーヤーの個性的なサウンドを、キーボードで直感的に演奏すること

C1 Compressor
コンプレッション、エキスパンジョン、ゲート処理まで対応する、フル機能のダイナミック・フィルタリング・プロセッサーです。

CLA MixHub
エンジニアのコンソール・ワークフローを完全再現する こんなプラグインは、かつてありませんでした。CLA MixHubは、スタジオの神話とも謳われた名エンジニア、クリス・ロード・アルジによる、濃密でなめらかなアナ

Clarity Vx DeReverb
AIを使って、どんな部屋でも、どんなボーカルでも使えるようにしましょう。Clarity Vx DeReverbがその作業を代行し、プロフェッショナルなサウンドのボーカルとダイアログのレコーディングを瞬時に、最高の忠実度で

Curves Equator
Wavesは30年間にわたりEQを設計してきました。しかし、もっと正確で、もっとパワフルで、もっと効率的で、さらに楽しいEQがあったらどうでしょう?近年、スタジオのテクノロジーとワークフローのほとんどすべての面